
【プロフィール】
佐藤 智香子(さとう ちかこ):新潟市中央区出身。放送局のアナウンサー時代に、生産現場を巡る取材を通して「食の世界」に魅せられる。退社後はフリーアナウンサーとして活動しながら、東京のフランス料理学校等で料理を学ぶ。2020年に「㈱ワイオリキッチン」を立ち上げ、「食」を通した幅広い事業を展開しながら、新潟の食文化を伝えている。
『新潟人246人目は、「㈱ワイオリキッチン」の代表取締役・佐藤智香子さんです。「新潟の食」や「料理の楽しさ」を伝えるために様々な事業に取り組まれています。アナウンサーから料理の道へ進んだきっかけや「新潟の郷土料理」への思いを中心にお話を伺いましたよ!笑顔でご対応いただき、ありがとうございました♪』
アナウンサーから料理の道へ
──アナウンサーから料理の道へ進んだ経緯を教えてください!
佐藤さん:アナウンサー時代に、生産現場を取材する機会が多くありました。生産のリアルな現場を見ているうちに、「新潟の食の底力」を実感するようになったんです。
そこから、「新潟の食材で色々な料理を作ってみたい」と思うようになりました。当時は若さ故の勢いがあったので(笑)、料理を学びに行こうと思いました。
──料理はどこで学ばれたのですか?
佐藤さん:東京・代官山にあるフランス料理の学校「ル・コルドン・ブルー」に入学しました。同学校の授業は、「フランス語」で行われるんです。
本国から運ばれてくる鴨を丸ごと捌くような、本格的なレストラン料理を学びました。どんどん料理にのめり込んでいきましたね。

──フリーアナウンサーとして活動しながら料理を学んでいたのですね!
佐藤さん:料理学校へは新幹線で通っていて、授業がある日以外はフリーアナウンサーとして新潟でロケや番組に出たりしていました。
2000年頃から、ステージで料理を作る“料理”と“話すこと”が一緒になったお仕事が多くなりました。
──「料理研究家」を目指していたのですか?
佐藤さん:特別目指していたわけではありません。好きで夢中になっているうちに“料理を作りながら話す”ということを周りの方に見つけていただいたのかもしれませんね。
そこからはTVやラジオに出て料理をしたりレシピを伝えたり、食に特化したトークショーやメニュー監修、ブランドプロデュースや飲食店立ち上げなど、色々やらせていただいています。料理を仕事にしようと気負わずに楽しんでいたけど、日々全力で向き合っていました。

【過去の新潟人はこちら】
▶【新発田市】“お客様に寄り添った料理”を提供する『カフェ&レストラン Cottonのオーナーシェフ・曽根原健さん』をご紹介♪料理の道を志したきっかけとは…!?
▶【燕市】けん玉の魅力を新潟に広げる『けん玉パフォーマーのGATAKENさん』をご紹介♪普及活動を始めたきっかけとは…!?
料理を気軽に楽しんで欲しい
──料理の楽しさはどんなところですか?
佐藤さん:例えば中国料理の調味料「XO醤」。干し貝柱などの上等な旨味のものがたくさん入っている醤(ジャン)で、ブランデーの最高峰の銘柄「XO」から付けられた最高の醤(ジャン)という意味があります。チャーハンに入れると格段に美味しくなるんですよ。
こんな風に、知らなかった調味料をひとつ知るだけで、興味の幅は広がります。私が料理の勉強をしていた当時は今ほど食の情報が溢れていなかったので、一つひとつの情報がとても新鮮で知識欲が高まりました。
──「知りたい」という探求心が強くなっていったのですね!
佐藤さん:今は、ネットで何でも知ることができるので、情報の消費が早いのですが、当時は足で稼いだ分だけ一つ一つにインパクトがあり、世界を広げてくれました。
その時代と料理の学びがシンクロしていたので、本当に“学ぶことが喜び”でしたね。「自分ならこうしたい」と考えることが楽しかったです。これは、今思えばどう魅力的に伝えられるかを考える、“喋り手の思考”と同じでした。

──佐藤さんから「料理は楽しい」ということが伝わってきます!
佐藤さん:食は“一生ついてまわるもの”なので、「せっかくなら、1食でも楽しめたらいいんじゃない」と思っています。
週末くらいは「あのレシピを作ってみようかな」とか。そういう仕掛けをもっともっと作りたいと思っています。
──料理をしようと思うのですが、忙しいと諦めてしまいます…(笑)
佐藤さん:そうですよね~。みんな忙しいし、美味しいお総菜もいっぱいあるのでそういう日があってもいいと思うんです。私も同じです(笑)。
でも、レシピを見て美味しそうと思ったら、時間のある時にちょっとやってみると、案外できて面白いと思うんです。だから「レシピは身近で簡単な方がいい!」と最近特に思っています。
──たくさんのレシピを考えるのは大変ではないですか?
佐藤さん:月30〜50のレシピ作りを10年以上続けていたので、大変といえば大変ですね(笑)。でも、煮たり、焼いたり、切り方や色の組み合せを考えたり、料理はクリエイティビティに溢れていて、やっぱり面白いんです。
“料理は時代を映す”のでトレンドの空気感も大事にしています。

──レシピや商品開発、企業コンサルティング、フードスタイリングなど幅広いお仕事をされていますね!
佐藤さん:様々な仕事に携わらせていただくことで、「料理が好きだ」と再認識しています。喋り手だった経験も良い影響を与えていますね。
メディアに私が出ることで“料理の面白さが伝わる”のなら、この仕事をしていて良かったと思います。
──料理家として、大切にしていることは何ですか?
佐藤さん:「自分のアイデンティティを知る」、「持っている知識を把握すること」ですね。おにぎりの本を出版した際にオーストラリアやフランスでの仕事で、日本の食材について環境問題に結びつけた質問を受けることがありました。そのときに「自国を知ることの大切さ」を実感しましたね。
新潟の食材も“知っているようで知らないことが多い”ことに気が付いて…。新潟の食の歴史や醸造など、生まれ育った新潟のことはちゃんと伝えられるように知っておくことが大事だと思いました。

“新潟の郷土料理の伝道師”として
──新潟の生活情報誌「キャレル」では、「佐藤智香子はじめましての郷土料理」という郷土料理の連載をされていますね!
佐藤さん:これまでたくさんのレシピを考案してきましたが、上京した娘が帰省した時に、「のっぺを食べたい」と言ったんです。
その時に「次世代に伝えられるように新潟の料理をちゃんと知りたい」と思いました。親になり、子供も大きくなり、そういうターンになったと感じましたね。
──連載を通して感じたことはありますか?
佐藤さん:「能生の笹ずし」や「栃尾の煮菜」など定期的に各地のお母さんたちに取材させていただいています。郷土料理は地域によって全く異なり、特に雪深い地域は食文化が奥深くて面白いですね。
郷土料理を深掘りしていくと、昔の方々の暮らしが透けて見えてきて、ものには意味があることに気づきます。家庭料理は内なるものなので、誰かがバトンを繋いで行かないと「もっと早いスピードで郷土料理が途絶えてしまう」と感じています。
──確かに若い世代が郷土料理に作る機会は減っている気がします。
佐藤さん:この連載チームは、編集長をはじめ、カメラマンや撮影クルーも撮影した料理を後日、プライベートでも作っているんです。
このじわじわとした浸透が郷土料理の魅力で、「生まれ育った土地や親、おばあちゃんに想いを馳せる素敵な時間」になるんです。難しいですが、やっていて本当に楽しいです。

──印象に残るエピソードを教えてください!
佐藤さん:SNSやイベントでお会いした方から、「佐藤さんレシピで我が家の食卓は成り立っています」、「料理が好きになりました」という声をいただいた時は嬉しかったです。
また、おにぎりのお仕事も多く、東京(大塚)のおにぎり屋さん「ぼんご」の女将・右近由美子さんと新潟食材を使ったコラボおにぎりを作って、同店のメニューにしてもらったことは心に残るお仕事でした。
──最後に、今後の目標を教えてください!
佐藤さん:古い本をよく読んでいるのですが、“新潟県の郷土料理”をもっと深く知りたいですね。この春から新潟日報メディアシップで、「誌面の料理を実際に作るリアル料理教室(年4回)」が始まるので、気軽に参加していただけたら嬉しいです。
そして、米どころで生まれ育っているからこそ、いつか「米とおにぎりを通して世界中の人と仕事ができたら」という夢があります。
>>>新潟日報カルチャースクールの講座「はじめましての郷土料理(春編)」の詳細はこちら



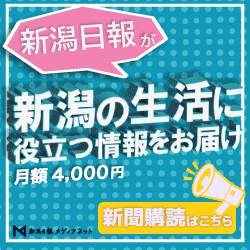





















新潟の郷土料理をもっと知りたくなったわ!佐藤さんの料理教室に行ってみようかしら♪